おすすめ記事
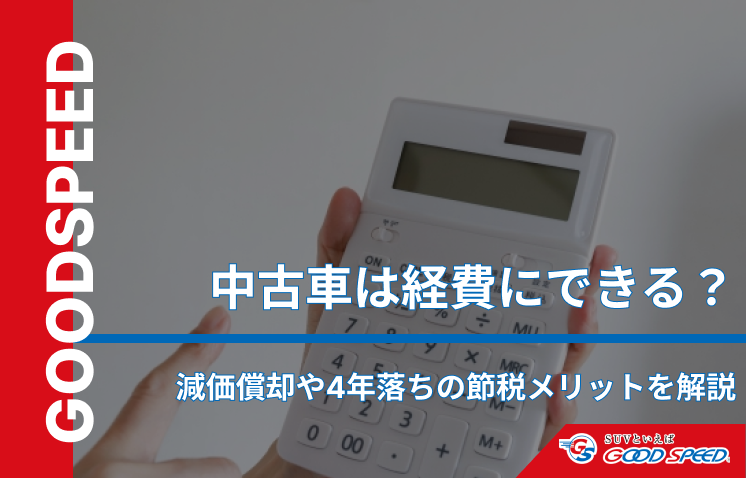
法人や個人事業主の方が事業用に中古車を購入した場合、車両本体価格や維持費を経費として計上することで、所得税や法人税の節税につながります。
特に中古車は減価償却の仕組みを正しく理解すれば、新車よりも大きな節税効果が期待できるでしょう。
本記事では、中古車を経費にするための基本的な考え方から、節税の鍵となる「減価償却」と「耐用年数」の仕組みを解説します。
目次
①車両の購入代金
②税金・保険料
③日々の維持費(ガソリン代・駐車場代など)
中古車の減価償却と節税の仕組み
減価償却の基本と耐用年数とは?
中古車の耐用年数の計算方法(簡便法)
「4年落ち」の中古車は節税に有利なのか?
中古車を経費にする際の勘定科目と仕訳例
購入時の仕訳(車両運搬具)
維持費の仕訳(旅費交通費・車両費など)
決算時の仕訳(減価償却費)
中古車を経費にする際の、3つの注意点
個人事業主は「家事按分」が必要
ローンやリースで購入した場合の扱いは?
10万円未満の中古車は一括で経費にできる
税務調査で慌てない!中古車の経費計上で指摘されやすいポイント
家事按分の根拠を明確にする
事業内容と車両価格の妥当性を説明する
まとめ
中古車は経費にできる!対象となる費用の種類一覧
事業用の車にかかるコストは、購入費から維持費まで幅広く経費にできます。
どこまでが経費として認められるのか、その範囲を正確に把握することが重要です。
以下では、①車両購入代金、②税金・保険料、③日々の維持費の3つの観点から、経費にできる費用の種類を解説します。
①車両の購入代金
車両本体価格だけでなく、事業で使えるようにするためにかかった費用(付随費用)を合算した「取得価額」が、経費の元となります。
付随費用には、納車費用、各種手数料、購入時に課される環境性能割などが含まれます。
②税金・保険料
自動車税や自動車重量税、購入時の環境性能割といった各種税金も、事業用の支出として経費の対象になります。
また、法律で加入が義務の自賠責保険料や、任意加入の自動車保険料も同様です。
これらは「租税公課」「保険料」などの勘定科目で、支払った期に経費として処理します。
③日々の維持費(ガソリン代・駐車場代など)
事業で車を走らせるためのガソリン代、高速道路料金、駐車場代も経費です。
その他、安全を維持するための車検代、点検費用、オイル交換代なども経費として認められます。
これらの維持費は業務で使った分だけを「旅費交通費」などの勘定科目で、こまめに記帳することが大切です。
中古車の減価償却と節税の仕組み
中古車の節税効果を最大化するためのポイントが、減価償却です。
新車より短い耐用年数が適用されるため、単年の経費額を増やせる可能性があります。
耐用年数がどう決まるのか、節税につながる仕組みなどを掘り下げていきます。
減価償却の基本と耐用年数とは?
減価償却とは、高額な固定資産の購入費を法律で定められた使用可能期間(耐用年数)で分割して計上する会計ルールです。
新車の普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、中古車の場合は経過年数を基に所定の計算式で残存耐用年数を算出し、その年数を適用します。
中古車の耐用年数の計算方法(簡便法)
中古車の耐用年数は、「簡便法」という計算式で算出できます。
法定耐用年数から経過年数を引いたものに、経過年数の2割を加算する方法です。(計算結果が2年未満の場合は2年)
簡便法での計算によって、中古車は新車よりも短い期間で償却できるケースが多くなります。
「4年落ち」の中古車は節税に有利なのか?
「4年落ち」の中古車が節税に有利なのは、耐用年数が2年になるためです。
法定耐用年数6年の車を上記の簡便法で計算すると、耐用年数は2年と算出されます。
新車の3分の1の期間で償却できるため、各年の経費計上額が大きくなり、結果として節税効果が期待できます。
中古車を経費にする際の勘定科目と仕訳例
中古車を経費にするには、簿記の知識である「勘定科目」と「仕訳」についての理解が欠かせません。
費用の内容を示すラベルである勘定科目は、購入時、維持費支払い時、決算時で異なります。
以下では、各シーンでの具体的な記録(仕訳)方法を解説します。
購入時の仕訳(車両運搬具)
中古車を買った際には、購入代金を「車両運搬具」という固定資産の勘定科目で処理します。
例えば150万円の車を現金で買えば、借方に「車両運搬具 150万円」、貸方に「現金 150万円」と記録します。
この時点では資産の移動であり、まだ費用にはなっていません。
維持費の仕訳(旅費交通費・車両費など)
日々の維持費は、内容に応じて「旅費交通費」や「車両費」などに振り分けます。
ガソリン代や高速代は「旅費交通費」、車検代や修理代は「車両費」「修繕費」などで管理すると分かりやすいでしょう。
例えば、ガソリン代5,000円なら借方「旅費交通費 5,000円」、貸方「現金 5,000円」と仕訳します。
決算時の仕訳(減価償却費)
決算期末には、その期に使用した価値の減少分を費用計上するために、減価償却の仕訳を行います。
償却費が50万円なら借方「減価償却費 50万円」、貸方「車両運搬具 50万円」(直接法)と記録します。
この仕訳によって、購入代金の一部が費用として計上されます。
中古車を経費にする際の、3つの注意点
有効な節税策である中古車の経費計上ですが、税務署に否認されないよう、守るべきルールがあります。
事業と私用の区別である「家事按分」、支払い方法による扱いの違い、少額な車の特例など、間違いやすい3つの重要ポイントを解説します。
個人事業主は「家事按分」が必要
事業と私用で車を共用する場合、全額を経費にはできません。
走行距離などの客観的なデータに基づき、事業で使った分だけを算出する「家事按分」が必要です。
この按分比率の根拠は、税務調査で問われる重要項目でもあります。
対策として、いつ・どこへ・何の目的で・何km走行したかを記録する「運転日報」を作成しておくとよいでしょう。
日々の記録が経費計上の正当性を証明する、何よりの証拠となります。
ローンやリースで購入した場合の扱いは?
支払い方法にも注意が必要であり、ローン返済額のうち経費にできるのは利息分のみで、元金は対象外です。
一方、リースであれば基本的に月々のリース料が経費となります。
また、10万円未満で購入した車は減価償却が不要で、その年の経費として一括処理が可能です。
10万円未満の中古車は一括で経費にできる
取得価額が10万円未満の資産は「少額減価償却資産」として、購入・使用開始した年に全額を消耗品費などで経費計上できます。
減価償却の手間が不要で、すぐに節税効果を得られるのがメリットです。
青色申告の中小企業者等であれば、30万円未満までこの特例の対象が広がります。
税務調査で慌てない!中古車の経費計上で指摘されやすいポイント
税務調査では「本当に事業のためか」という視点で、中古車の経費計上の中身を厳しくチェックされます。
特に「家事按分の根拠」と「車両価格の妥当性」は、指摘を受けやすいポイントです。
万が一経費として否認されれば、追徴課税のリスクもあります。
以下を参考にして、事前にしっかり対策を講じておきましょう。
家事按分の根拠を明確にする
税務調査で厳しく見られるのが、家事按分の妥当性です。
先ほど紹介した通り、口頭での説明だけでは不十分なため、運転日報のような客観的な記録が不可欠です。
資料作成の習慣を身につけて、税務調査が入っても問題なく対応できるように備えましょう。
事業内容と車両価格の妥当性を説明する
事業内容とかけ離れた高級車や趣味性の高い車は、事業との関連性を疑われる原因になります。
税務調査で「なぜこの車が必要なのか」と問われた際に、合理的な理由を説明できなければなりません。
例えば、「重要な顧客を送迎するためにセダンが必要」という説明は認められるかもしれません。
一方で、在宅ワーカーがハイスペックなスポーツカーを経費に計上するのは、難しい可能性があります。
事業と車の関連性を客観的に、かつ論理的に説明できるかが重要です。
まとめ
中古車の購入時には、正しく経費計上することで大きな節税効果が期待できます。
車両代金だけでなく、税金や日々の維持費も経費の対象となるのがポイントです。
特に減価償却の仕組みを理解し、耐用年数が短くなる中古車のメリットを活かすことが重要となるでしょう。
節税効果を高めるには、家事按分の徹底や客観的な証拠資料の保存といった日々の適切な経理処理が必要です。
本記事で解説したポイントを押さえ、もし判断に迷うことがあれば税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
よくある質問
Q1.期の途中で中古車を購入した場合、減価償却費は月割り計算になりますか?
はい。原則として事業で使用を開始した月から、期末(または年末)までの月数に応じた「月割り計算」が必要です。
例えば、決算が3月の法人が1月に車を購入してすぐに事業で使い始めた場合、その年度に計上できる減価償却費は1月〜3月の3ヶ月分となります。
Q2.購入時に付けたカーナビやドライブレコーダーの代金も、経費になりますか?
はい。事業で使うために車両と一体で取り付けたカーナビやETC、ドライブレコーダーなどの費用は、車両本体の価格に含めて「取得価額」として資産計上し、減価償却を通じて経費にしていきます。

Copyright © GOOD SPEED.








