おすすめ記事
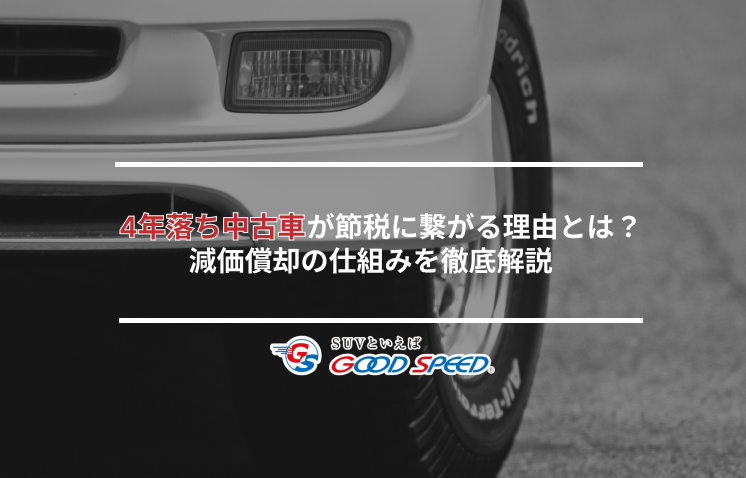
「中古車の購入が節税に繋がると聞いたけど、理由がよく分からない」そんな疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、4年落ちの中古車が節税に有利な理由と共に、減価償却の仕組みや計算方法を分かりやすく解説します。
節税効果を最大化する具体的な手法や、個人事業主のケースについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
4年落ちの中古車購入が注目される理由
全額を経費として一度に計上できる
状態の良さにも期待できる
減価償却に関する基礎知識
減価償却とは
減価償却費を求める式
取得価額
償却率
耐用年数の算出方法
減価償却費の計算方法は2つ
定額法を選択した場合
償却率は耐用年数を用いて計算
定額法による減価償却費のシミュレーション
定額法を選択するメリット
定率法を選択した場合
償却率は「定率法の償却率」を参照
定率法による減価償却費のシミュレーション
定率法を選択するメリット
4年落ちの中古車を購入して節税効果を最大化するには
定率法を選択
決算月の翌月に購入
ローンで購入した場合
4年落ちの中古車を個人事業主が購入した場合
定率法の適用は事前申請で可能
プライベートでの使用がある場合は注意
定額法でも節税効果が得られるケースはある
まとめ
4年落ちの中古車購入が注目される理由
中古車、特に「4年落ち」の車が、個人事業主や企業の間で注目を集めています。
その理由は、以下のとおりです。
全額を経費として一度に計上できる
一般的に、車を購入しても、すぐにその全額を経費として処理することはできません。
しかし、4年落ち中古車の場合、条件によっては購入した年度に全額を経費として計上できる可能性があります。
この点が、4年落ちの中古車購入において、節税に有利だと言われるポイントです。
状態の良さにも期待できる
もうひとつの理由として、最大の節税効果を得ながら、状態の良さにも期待できる点があります。
実は、4年落ち以降の中古車であれば、何年落ちであっても節税効果は変わりません。
しかし、古い車になるほど機械部品の劣化は進んでおり、故障するリスクも高い傾向にあります。
つまり、全額を経費として計上できる可能性がありながら、もっとも高年式となるのが4年落ちの中古車というわけです。
減価償却に関する基礎知識
4年落ち中古車の購入が節税に有利となるのは、「減価償却(げんかしょうきゃく)」という会計上の手続きがあるからです。
ここでは、減価償却に関する基礎知識を解説していきます。
減価償却とは
減価償却とは、購入した資産の価値を複数年に分けて少しずつ経費として計上する方法です。
建物、機械、車両など、時間の経過によって価値が減少していく「減価償却資産」の取得費用は、使用する期間すべてで分割し経費計上すべきとされています。
減価償却費を求める式
実際に経費として計上できる額を減価償却費と呼び、具体的な金額は以下のような式で求められます。
取得価額 × 償却率 = 減価償却費
「取得価額」と「償却率」の内容は、以下のとおりです。
取得価額
中古車を購入する場合で、取得価額に含まれるのは以下の項目です。
車両本体価格
オプション品
納車費用
未経過自動車税の相当額
未経過自賠責保険料の相当額
中古車を購入する場合で、取得価額に含まれないものは以下のとおりです。
自動車重量税
任意保険の保険料
リサイクル料金
中古車を購入する場合で、取得価額に含めるかどうか選択できるものは以下のとおりです。
登録費用(車庫証明費用や申請代行費用など)
自動車環境性能割
償却率
償却率とは、その資産の価値が1年間でどのくらい減少するのかを示す、割合の数値です。
減価償却資産の耐用年数と、選択した計算方法に応じて変化します。
耐用年数の算出方法
減価償却費の計算に必要な「償却率」の値は、国が定めている減価償却資産の「耐用年数表」を用います。
中古で資産を購入する場合は、時間の経過によって減少した価値を考慮して、新たに耐用年数を算出しなければなりません。
中古車の耐用年数を算出する式は、以下のとおりです。
(新車の耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 0.2 ※小数点以下は切り捨て
4年落ちの中古車だと、以下のような結果になります。(普通車の耐用年数は6年)
(6年 − 4年)+ 4年 × 0.2 = 2年 + 0.8年 = 2.8年 → 小数点以下は切り捨てて2年
減価償却費の計算方法は2つ
減価償却費の計算方法は「定額法」と「定率法」という2つの選択肢があります。
ただし、建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアは、定額法で計算しなければなりません。
そのほか(中古車を含む)に関しては、個人事業主は定額法を選択し、法人は定率法を選択するという原則的なルールがあります。
定額法を選択した場合
定額法を選択した場合、毎年同じ金額を経費として計上していく流れになります。
償却率は耐用年数を用いて計算
定額法を選択した場合の償却率は、以下のように計算されます。
1 ÷ 耐用年数 = 定額法の償却率
耐用年数が6年の場合だと1 ÷ 6で、償却率は 0.166・・・です。
割り切れない場合は、国税庁が示す「減価償却資産の償却率等表」から「旧定額法、定額法の償却率表」を参照します。
表を参照すると、耐用年数が6年の場合、償却率は0.167となります。
定額法による減価償却費のシミュレーション
定額法で減価償却費を計算した場合のシミュレーションは、以下のとおりです。
500万円の新車(耐用年数6年)を購入した場合
償却率:1 ÷ 6 = 0.167
減価償却費:5,000,000 × 0.167 = 835,000
1年目:835,000円
2年目:835,000円
3年目:835,000円
4年目:835,000円
5年目:835,000円
6年目:824,999円(資産を継続利用する場合は、全額償却せずに1円を残す)
定額法を選択するメリット
減価償却すべき額が毎年均等になる定額法には、以下のようなメリットがあります。
シンプルな計算で、会計処理がやりやすくなる
定率法と比較すると償却額が小さいので、初期の経費を抑えられる
定率法を選択した場合
定率法を選択した場合、減価償却費は年ごとに減っていく流れになります。
初年度に、多くの金額を経費として計上できる点が特徴です。
償却率は「定率法の償却率」を参照
定率法を選択した場合、償却率は国税庁が示す「減価償却資産の償却率等表」を参照します。
定額法とは異なり、償却率を算出するための計算式は使用しません。
表内にある「旧定率法、定率法の償却率等表」から、購入した資産の耐用年数に応じた値を参照します。
定率法による減価償却費のシミュレーション
定率法で減価償却費を計算した場合のシミュレーションは、以下のとおりです。
500万円の新車(耐用年数6年)を購入した場合
償却率:0.333
減価償却費:5,000,000 × 0.333 = 1,665,000
1年目:1,665,000円を償却、残金は3,335,000円
2年目:3,335,000 × 0.333 = 1,110,555円を償却、残金は2,224,445円
3年目:2,224,445 × 0.333 = 740,741円を償却、残金は1,483,704円
以降も同じ方法で減価償却を繰り返す
残金が償却保証額を下回ったら、計算方法を切り替えて減価償却を継続
資産を継続利用する場合は、全額償却せずに1円を残す
償却保証額は「取得価額 × 耐用年数に応じた保証率」で計算します。
「取得価額 × 定率法の償却率」で、償却保証額を下回る値が算出されたら、そこで「改定取得価額 × 改定償却率」の式に切り替えなければなりません。
「改定取得価額」に入るのは、償却保証額を下回った年度の残金です。
「耐用年数に応じた保証率」や「改定償却率」は、国税庁の償却率等表で参照できます。
定率法を選択するメリット
減価償却費が年ごとに減少していく定率法には、以下のようなメリットがあります。
初年度に多くの経費を計上でき、高い節税効果が得られる
初期の税額が抑えられるため、資産に投じた費用を早期に回収できる
4年落ちの中古車を購入して節税効果を最大化するには
記事の冒頭で解説したとおり、4年落ちの中古車であれば節税効果を最大化することが可能です。
実際に4年落ちの中古車を購入し、初年度で全額を経費に計上するための条件を見ていきましょう。
定率法を選択
条件のひとつめは、減価償却費の計算方法に定率法を選択していることです。
その場合、減価償却費は以下のように算出できます。
例)300万円で4年落ち中古車を購入
4年落ち中古車の耐用年数は2年、定率法の償却率は1.0
1年目:3,000,000 × 1.0 = 3,000,000
購入価格と同額の減価償却費を初年度に計上できる
※実際に計上するのは2,999.999円
計算方法が異なる定額法では、上記のような計上はできない点を認識しておきましょう。
決算月の翌月に購入
次に重要な条件となるのが、決算月の翌月に購入することです。
年度の途中で購入した場合、1年目の減価償却費は月割りで計算しなければなりません。
決算月の翌月に購入することで1年間フルに減価償却できるため、節税効果は最大になります。
ローンで購入した場合
中古車をローンで購入した場合でも、減価償却は可能です。
ただし、利息部分は別途「支払利息」として処理する必要があります。
元本は減価償却し、ローンの金利は「支払利息」の勘定科目で経費に計上しましょう。
4年落ちの中古車を個人事業主が購入した場合
原則として定額法を選択しなければならない個人事業主は、中古車購入の節税効果は得られないのでしょうか?
4年落ちの中古車を、個人事業主が購入するケースについて解説していきます。
定率法の適用は事前申請で可能
個人事業主であっても、定率法の適用は事前申請で可能です。
届出書は2種類あるので、状況に応じて適正な書類を税務署に提出しましょう。
減価償却資産の償却方法の届出書
・新たに事業を始めるとき
・これまで取得していない資産の種類で定率法を選択しようとするとき
減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
・これまで取得したことのある資産の種類で、今までとは異なる償却方法を選択したいとき
これらの書類を提出しないと、中古車については自動的に定額法になりますので注意しましょう。
プライベートでの使用がある場合は注意
個人事業主であれば、仕事とプライベートの両方で車を使うことが想定できます。
プライベートでの使用がある場合は、家事按分と呼ばれる算出方法を用いて、事業で使った分だけを経費としなければなりません。
使用の7割が仕事であれば、減価償却費として計上できるのは取得価額の70%だけで、残りは事業主貸で処理します。
定額法でも節税効果が得られるケースはある
減価償却すべき額が毎年均等になる定額法でも、より高い節税効果を得られるケースがあります。
それは耐用年数が6年の新車と比較した場合です。
以下のように、同じ予算であれば4年落ち中古車を購入することにより、1年あたりの償却費をより多く計上できます。
180万円の新車(耐用年数6年)
1年あたりの償却費:30万円
180万円の4年落ち中古車(耐用年数2年)
1年あたりの償却費:90万円
まとめ
4年落ちの中古車は節税に有利な面を持つため、法人の事業用資産としては魅力的な選択肢です。
減価償却の考え方を理解し、適切な計算方法を選ぶことで、より大きな節税効果が期待できます。
個人事業主であっても、事前に申請しておけば同様の節税効果を得ることが可能です。
購入タイミングにも注意し、自身の事業に合った償却方法で車両の導入を進めていきましょう。
よくある質問
Q1.中古車購入を経費に計上する場合、4年落ちが有利と言われますが、5年落ちや6年落ちが当てはまらないのはなぜですか?
5年落ちや6年落ちでも節税効果は同じですが、良い状態の車に出会える可能性が低くなるからです。
状態が悪くなるほど取得価格は下がる傾向にあり、実質的に経費として計上できる金額も少なくなります。
Q2.軽自動車の場合も、4年落ちが節税に有利なのですか?
中古の軽自動車を購入する場合、2年落ちの車両から取得価格の全額を経費として計上できます。
ただし、定率法を選択していること、決算月の翌月に購入して使用開始していることが条件です。

Copyright © GOOD SPEED.








